『同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか』(2/4)

前回の続きです。
今回も本の中でいくつか同調圧力に関する事例について特に印象に残った部分の続きを紹介します。ここでは、
Q みんな同じ時間を生きている
Q 絶対に否定されない「正義の言葉」
Q 人を見極められない日本人
この3つをピックアップして紹介し、またみなさんと一緒に日本の同調圧力の問題について考えていきたいと思います。
Q みんな同じ時間を生きている

まずはQみんな同じ時間を生きていることについて話していきます。
日本の同調圧力というのは昔からありました。
1940年頃は、当時の新聞に「ぜいたくは敵だ」「兵隊さんのことを思えばぜいたくはできません。」と書かれていたようです。
これって何を表しているのかというと「わたしたちは同じ時間を生きている」という感覚があるということです。
そもそも社会というのは、個人と個人が集まってできるものです。
でも日本人の場合は、個人が集まって社会が成り立っているという考え方ではなく、みんな同じ仲間というか、同族意識、村社会、みんな一緒みたいな感覚で生きているという感じです。
だから「みんながそうしているから、あなたもそうするべきだよね」という論理が成り立つわけです。

また、当時の新聞には「日本人ならぜいたくはできないはずだ」と書かれていたものもあったようです。
「日本人なら」という表現をする時点で、日本は村社会だというのがわかりますね。
その村社会の文化はまだ今でも残っていて、新型コロナウイルスでついに日本人の生態が浮き彫りになったというのがはっきりしたということです。
これに関連して、本から抜粋した部分を紹介します。

みんなが同じ時間を生きているという感覚は、日本人独特なものらしいですね。
例えば上司よりも先に帰るのは気が引けるとか、会議がなかなか終わらないというのも、この「みんな同じ時間を生きている」からという同調圧力のせいなんだなということがわかりました。
Q 絶対に否定されない「正義の言葉」

次はQ絶対に否定されない「正義の言葉」についてです。
日本の同調圧力の高さは国際的に見ても軍を抜いています。
日本はそもそも法治国家なので、人を裁いていいのは法律だけなんです。
以前、一般人が他県からきた車のナンバープレートを壊したり、営業してはいけないという張り紙をはったりといった自粛警察だとかありましたが、権限を持たない市民が勝手に人を裁いてはいけないんです。
なんのために難しい試験をうけて裁判官になった人がいるのか、裁判所があるのかという話だと思います。
ただ、「正義の言葉」というのは誰にも否定されないので、堂々といえてしまうということになります。
また、上司とか同僚とかより早く帰りづらいのは、「みんな同じ時間を生きている。みんな同じ仲間だ。だから他人とは違うことをするな」という同調圧力があるためです。

海外のように、「社会というのは個人と個人があつまって構成されているものだ」ということができない。
自分は自分、他人は他人ということができないから、早く帰った人に対して文句をいっている人がいる。
それから同調圧力が強い環境の中にいると、多くの社員が「上司や仲間が残業しているから帰りにくい」と感じてしまいます。
また「残業していると評価される」と考える社員も多く、サービス残業や休日出勤をしても構わないという姿勢が企業に対する忠誠心と思い込んでいる場合もあります。
それは経営者や管理職がそういう価値観のために起きる現象なのですが、社員がその空気を読んでその価値観にあわせて働いてしまうというのがあります。
どうしてこういったことがわかるのかとういことっですけれど、鴻上さんはこのように答えています。

正義を盾にして何かをいいたがるのは、こういった背景があったんだなというのを感じました。
Q 人を見極められない日本人

最後はQ人を見極められない日本人についてです。
この本では総務省の『情報通信白書』(2018年版)について、欧米諸国に比べ日本は他人への不信感が強いという調査結果も紹介されています。
具体的には「SNSで知り合う人たちのほとんどは信用できる」かの問いに対して「そう思う・ややそう思う」が日本では1割ほどですが、ドイツでは約5割、アメリカは約6割、イギリスでは約7割に上るようです。

人間を信用している日本人は、全体の1割しかいないというのはとても驚きました。だからネットで「炎上」がくりかえされるのも当然なのかなと感じました。
質疑応答・感想など

A 今回の発表をきいて、自分が周りに同調圧力をかけていないか気になりました。
私が勤めている会社では、会議が終わったらみんなが片付ける。最近の人たちってそそくさと帰る。片付けをせずに。その光景を見たときに、なんであいつらだけ帰るんだって思うんですよね。
そういう意味では同調圧力だったのかなって思います。
Q 日本人って自己責任ってところは弱いのかな。
「みんな残業してる」とか「自分の分が終わったなら手伝ってほしい」という人がいる。
でも冷静に考えれば、これはその人の能力が足りていないから残業している。
あと上司も「定時で上がるの?」といいますが、定時で帰っている人はやることやってるんだから、評価されるべきはその人。長く残業して残る方がいいとういのは、評価基準が間違っていると思います。
すべては自分の責任で動いているという意味では、欧米の人よりは弱いのかもしれませんね。
Q 飲食店とかに貼り紙するのも疑問ですね。
自分が感染症にかかりたくないならそこにいかなければいい。だから、「みんなが自粛してるんだからお前も自粛しろ」というのはおかしい。
Q マスクの問題もありますよね。これから熱中症の危険性を考えると、場所によってはマスクは外したほうがいい。熱中症で倒れる方がリスク。
A あとやっぱり人を見極められない部分も日本人にはあると思います。
人を見極められない理由として、佐藤さんは、「日本では世間の中の身分や地位で判断してきたため、自主的に判断する能力が、日本では育たなかったことを意味します。」とあります。
たしかにその通り。ただ私もこれに加えてあると思うのが「自分で調べる人がいない」、「メディアリテラシーがない」というのもあると思います。
良いことをいっているけど中身は全くないというものある。日本人の勉強時間のデータで日本人は圧倒的に少ないらしい。

1日平均勉強時間6分。それも人を見極められない原因の一つ。1日10分勉強すれば人は日本人は上に行ける。
これがちょっと変な同調圧力がある原因だと思いますね。
A 私は体育の授業で集団行動が一番嫌いだったんですよね。
「なんで右向け右って言われて、右を向かないといけないの?」「だってみんな右向いてるから」っていう。凄い不思議だなって思っていましたね。
Q ちなみにうちでは新年度に社長のあいさつがあって、その時に一同起立っていってみんな立つのですがそれも嫌ですか?
A 嫌です。大嫌いです笑。社長にあいさつしたい人が個別に挨拶にいけばいいと思います笑
2022/04/09
鴻上 尚史,佐藤直樹『同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか』(2/4)


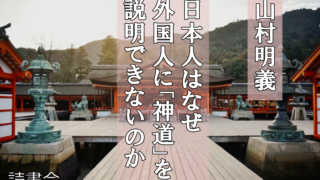


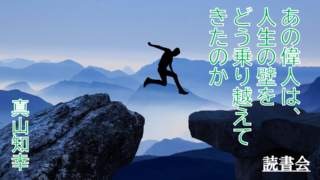

コメント